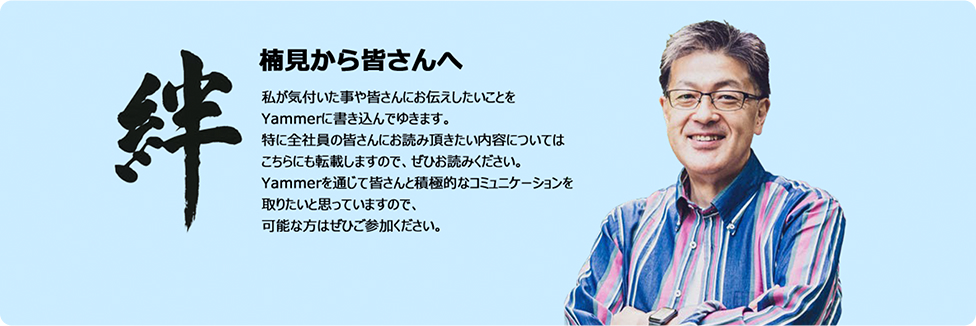
2023年11月8日
PCO社 プロセスオートメーション事業部甲府工場を訪問しました(10/13)
皆さん、お疲れ様です。
先週10/13には、前回の訪問以来2年ぶりに甲府工場を訪問しました。
その記事には記さなかったのですが、前回のプロセスオートメーション事業部(PABD)訪問時には安全道場の設置と、派遣・請負社員の皆さんを含めた全員教育をお願いしました。
以来、甲府工場では、多面的に対策に取り組んでくれていますが(写真①)、今年度もまだゼロ災には到達していません。設備安全や安全手順の徹底は当然ですが、それでも一人でも意識が欠けていれば労働災害は発生します。「安全は全てに優先する」を一人残らず全員に徹底すべく、愚直な全員教育の継続と意識を途切れさせない工夫を重ねていただきたいと思います。
さて、実装機の事業は、今は中国の市況悪化の影響を受けて非常に厳しい状況にありますが、甲府工場ではそれを機会と捉えてモノづくりの進化に取り組んでくれています。考え方そのものも2年前とは様変わりで、2030年の販売・利益目標を達成するために生産性を160%まで引き上げる目標からのバックキャストでの取り組み。工程のロス、ムダ、バラつきをデジタルで見える化して改善のサイクルが回るようになっています。これらは大きな進化。
ただ、2030年の目標というのは、あくまで自分目線の目標にしか過ぎないわけですから、ひょっとするとその目標を2年も3年も前倒しで達成しなければならないかもしれません。なので、やはり、自分目線での目標達成を目的化するのではなく、高い目標をいかに早く達成するか、そのためにも、日々、「改善後は改善前」という考え方で取り組んでいただくことを期待するわけです。そういう意味では、2年前には見当たらなかったWIPボードも技術・工程のあちこちで活用(写真②)してくれていることも確認しましたので、そういう考え方や取り組み姿勢が始まりつつあると感じました。
ただ、工程の改善のWIPボード活用でありがちな話ですが、標準作業が決まっていてその通りの標準時間に届かないときに課題として挙げるような運用。これはWIPボードの活用レベルとしてはレベル1とか2。それだと、標準時間から進歩しないのです。標準時間をさらに短縮するには、ここがボトルネックだという課題がどんどん上がってくるということを、全員が意識する。全員が意識するためには7つのムダの視点を全員が持つことが非常に大事。例えば、自分が物を右から左に運んだり、ワークを持ち替えていたり、そのこと自体がムダでそれをなくすためには・・・という考え方で皆さんが提案をしていくようになれば、甲府工場の進化が継続するようになると期待するのです。
また、TOCのCCPM(参考図書※)にもチャレンジいただいているとのこと。これも、大いなる進化。CCPMもサバ取りをしてその目論見通りに期間を短縮するには、課題の一個流しを皆で徹底実践するのが絶対条件。
さらに、甲府ではこれも2年前にはなかった大部屋活動も始めてくれていますが、工場全体を見渡した時のモノと情報の整流化、まずはモノと情報の流れ図に基づいて、どこにどれだけの滞留があるのかを見える化して取り組めば、甲府工場全体で取り組んでいるTOCやTPS(※)の活動、PG Wayの取り組みはまだまだ進化できると思います。
一方、実装機の事業の未来を考えた時に私が気になっているのは、デバイスの微細化の進化がどこまで続くのかです。現在の高密度基盤に実装される積層セラミックコンデンサは、0402(0.4×0.2mm)から0201(0.25×0.125mm)まで小型化され、さらにデバイスメーカーからは01005(0.125mm×0.063mm)のサンプルが出始めていますが、それ以上の微細化はマウンターでの実装に適するのかどうか?それ以降は半導体プロセスのような技術の出番になるのであれば、マウンターの領域は技術進化が継続せず、いずれ当社の強みはキャッチアップされてしまうのではないか、と懸念しています。
半導体の微細化についても、数年前の中国は2周3周遅れであったのが、華為技術傘下HiSiliconのKirin820で7nmができており、周回遅れくらいまでキャッチアップしてきています。早晩中国メーカーが力をつけてくることが想定されますし、「中国で勝てないとグローバルで勝てない」というのはこの業界でも同じだと思うのです。
そういうことを事業部長の秋山さんに申し上げると、力強い返事が返ってきました。それが、昨年リリースされたNPM-Gシリーズの中のNPM-GH(写真③)だというのです。私が懸念しているような点も見越して製品の進化を図っていただいていることは心強い限り。
未来を見渡した上での戦略的な製品の進化と、弛みなき現場のオペレーション力強化の加速を継続すれば、今は市況の影響で苦しくとも、遠からず甲府工場、PABDが以前にも増して力強く羽ばたける日が来ると確信します。
GO! GO! PABD! やっちゃえ!甲府工場!
※このリンク先は、パナソニックグループ外の外部サイトになります。サイトの内容については、当社は一切責任を負いませんのでご了承ください。

写真①

写真②

写真③
※このサイトはパナソニックグループで働く皆さんが、ご自身のワークスタイルやライフスタイルに合わせて、イントラネットにアクセスできない状況でもグループの情報に触れることができる環境を構築することを目的としています。
本ページのURLや、掲載されているコンテンツを許可なく外部と共有したり、SNS等に掲載したりすることのないよう、取扱いは十分ご注意ください。

