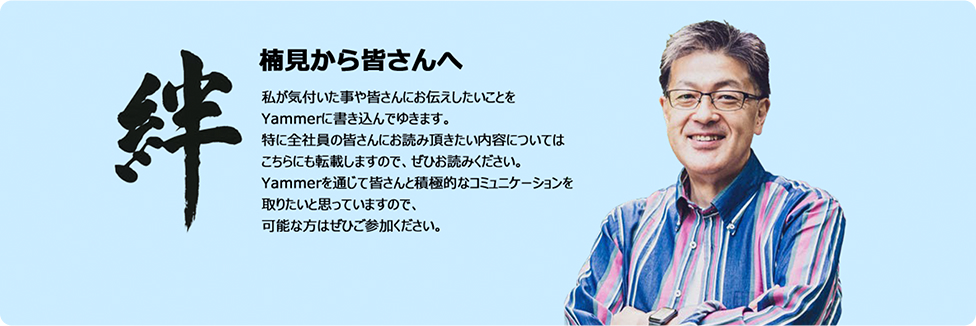
2023年3月28日
テクニクス西門真拠点を訪問しました(3/7)

写真①
今回の訪問記は長文ご容赦を。
少々歴史の説明(というより蘊蓄?)から記したいと思います。
Technicsブランドは、ちょうど私の生まれた年と同じ1965年に当時の松下電器の高級オーディオブランドとしてスタートしました。
当社のオーディオの歴史は1932(昭和7)年のスピーカー#265に端を発します。奇しくも1932年といえば、命知元年「真の創業」の年ですね。以来、Technicsブランド第1号の小型スピーカーTechnics1の発売に至るまでにも研究が積み重ねられ、様々な商品が発売されました(写真①「わが社のオーディオの歩み」・・・松風1971年9月号より抜粋)。過去の代表的な商品については、ミュージアムの2020年の企画展の中でも特集されていますので、興味ある方はこちらをご参照ください。
私がオーディオにのめり込み始めた中学~高校の時、Technicsのアンプやスピーカーは好みではなかったものの、ターンテーブルSP-10Mk2(※)とオープンリールデッキRS-1500U(※)は憧れの機器でした。そして、Technicsの代表といえばレコードプレーヤのSL-1200シリーズ(※)。1972年の初号機からレコードの再生のみならずクラブシーンのDJで使われ始め、2010年にTechnicsブランドをいったん休止した当時のMk6までアナログDJプレイのグローバルデファクトモデルで、累計350万台の販売がありました。
私が、初めてオーディオの事業を実際に担当したのは、別々の事業部であったテレビ、DIGA、オーディオを一つの「ホームエンターテイメント事業部」として統合して旧アプライアンス社に移管された2014年のこと。その時、事業の現場ではオーディオ事業の再生の手立てとしてTechnicsのブランドの復活の動きが既に始まっていました。具体的には復活に向けた商品ラインナップの検討や、技術試作が始まっていたのです。
しかし、ブランドだけ復活しても、それらの商品がお客様にお選びいただけるものでなければどうしようもありません。
技術としては、DIGA開発で積み重ねてきたユニークなデジタル領域での高音質化の研究や、GaN(窒化ガリウム)のパワー素子を用いて高いスイッチング周波数で動作するデジタルパワーアンプの先行開発も進めてもらっていたので、すぐには結実しないだろうが差別化のネタになる確信はありました。
一方、当時の状況は、アマチュア自作オーディオマニアの私が、試作機を試聴し、回路図を見て大きな課題に気付くレベルでしたから、「これは、相当にテコ入れしないとダメだが俺の手には負えないな。しかし挑戦はしたい・・・」と悩んでいる時で、当時旧AVC社の社長だった宮部さんから「小川理子さんにやってもらったらどうや?」と助け船を出してもらいました。
ちなみに、小川さんはジャズピアニスト(※)としても超有名ですが、小川さんが入社後の音響研究所時代に開発に携わられたフラットパネルスピーカーがウィーン国立歌劇場に納入されたり、楽器型スピーカーがニューヨーク近代美術館の永久展示品に選定されるなど、オーディオ開発の卓越した経験と実績もお持ちですので、Technicsは小川さんにリードしていただくことに即決しました。その後の話は小川さんの著書「音の記憶」(※)の後半に詳しく記されています。
そして、2014年秋に「Technicsブランドの復活」を発表、発表後小川さんの手元に海外から25,000を超えるファンの署名簿を含むSL-1200復活の嘆願書が届いたのです。私はその話を聞いた時、もう設備も資料も何も残っていない、しかもアナログ技術の塊のようなターンテーブルの復活など非常に難しいことが分かっていたので「ここは止めるべきか?」とも思ったのですが、小川さんが不安そうな中にも「これをやらねば!」との熱意と確信をもって「OBにも伝手があるから!」と仰ったことで、「じゃぁ、やってみようか」とGOをかけました。
それから間もなく2015年末で私はDIGA+オーディオの事業部長の役割も小川さんに引き継いで白物4事業の専任になり、テクニクスを離れることになりましたが、そこから実際に2016年SL-1200GAEでのターンテーブル復活まで、小川さんはじめテクニクスの皆さんの努力は壮絶なものであったと思います。
・・・長くなりましたが、ここまでが前置き・・・
それから7年余りを経て、3月7日に久しぶりにテクニクスの試聴室で最新の機材の視聴をさせていただき、また、若い社員の皆さんとの懇談の機会を得ました。
視聴はSL-1000R~SU-R1000~SB-G90Mk2、SL-G700Mk2~SU-G700Mk2~SB-G90Mk2など。
2015年のブランド復活の時とは全く違う次元の音、まさにアーティストが演奏に込めた魂が聞こえる感覚、過去の全盛期のテクニクスの弱点(=私が好きでなかった理由)を見事に克服した、もはや音の再生機ではなく音楽を奏でるオーディオに進化していることに驚きました。そしてその種明かしとして説明いただいた技術の進化、それはアナログ機器については徹底した振動や波面の制御、デジタル機器はまさにデジタルの領域での進化を弛みなく突き詰め続けてくれていたのです(写真②③)。これには、本当に涙ぐみそうになりました。
実際、それぞれの商品が、専門誌の評価でトップレベルの賞を受賞できるまでになっています(写真④)。
そして、商品をどんどん進化させ続け、事業としても成長を続け、独り立ちまであと一歩のところまで来ているテクニクスブランド事業推進室の若い社員の皆さん、テクニクスに携わりたくて集まった皆さんは、自信と誇りをもって商品や事業の進化に取り組んでくれています。むしろ、私が元気をもらったくらい。
その中の一人から「楠見さんは久しぶりに来られて、以前と変わったことと変わっていないことは何ですか?」と問われ、私は「変わったことは世代の交代。若い皆さんがこんなに活躍しているとは思わなかった。変わっていないことは、進化し続けていること。計測限界を超える領域でも仮説をたててデジタルの領域での改善に挑戦し続けてくれていること」・・・と答えながら、もう一度目頭を熱くしたのです。
テクニクス事業がここからスケールするには、認知や販路の拡大も必要ですし、そのためには各地域の販売部門に支援いただくことも必要ですが、専業の中にもこのような進化の武器を手にしているところは無いわけですから、是非ともトップスピードでの進化を続けていただき、確固たる事業に育てたいものです。
(※)このリンク先は、パナソニックグループ外の外部サイトになります。サイトの内容については、当社は一切責任を負いませんのでご了承ください。

写真②

写真③

写真④
※このサイトはパナソニックグループで働く皆さんが、ご自身のワークスタイルやライフスタイルに合わせて、イントラネットにアクセスできない状況でもグループの情報に触れることができる環境を構築することを目的としています。
本ページのURLや、掲載されているコンテンツを許可なく外部と共有したり、SNS等に掲載したりすることのないよう、取扱いは十分ご注意ください。

