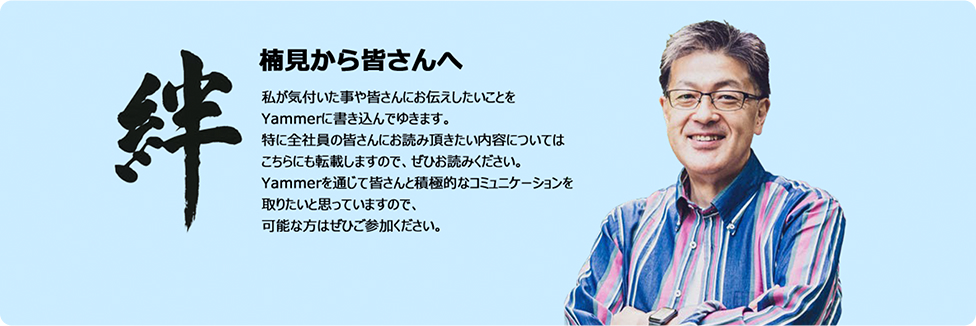
2020年10月26日
WIPボードに魂を入れ、課題は1個流しを

皆さん、おはようございます。
何度となく”WIPボード"という言葉を発信していますが、旧インフォ以外ではあまり活用されておらず、むしろ「よく知らない」という方もおられるようなので、今更ながらではありますが、改めて紹介をしておこうと思います。
WIPはWork In Processの略で、WIPボードはチームで仕事を進めるにあたってのタスクの状態を見せる化し、個々人の作業の滞留を早期に発見し、必要な支援を適時に実施するためのツールです。
WIPボードを運用している職場では、扱っている仕事によって様々に工夫したボードを使っていますが、典型的なボードの例を図として添付し、以下では、この図に沿って簡単に説明します。
まず、しっかりと段取りをして、着手前のタスクは「実行待ち」のところにタスクの附箋を貼りますが、この時にフルキット(そのタスクを着手する上で未確定の要素がない)になっているのかどうかを見極めて、フルキットになっていないタスクは着手しないようにすると同時に、フルキットにするための働きかけをしてゆきます。
この例では、フルキット済のものも含めて「実行待ち」のタスクが多いBさんは、実行中のタスクが滞留しているか、あるいは、今後負荷のかかりすぎになるリスクがないか、リーダーのAさんはよく注視してフォローしてゆかねばなりません。
各メンバーは「実行中」の作業以外はやってはいけません。AさんとDさんは、「実行中」のところに二つのタスクがありますが、これは望ましいことではありません。本来、「実行中」のところには一つのタスクだけが存在して、そのタスクに集中するのが理想的です。タスクの切り替えは、集中を阻害するし、頭の切替えに時間もかかりますのでムダに繋がるのが一般的であるためです。
そして、やってみて壁にぶち当たったときは、躊躇せずに「助けて!」のところに附箋を移動します。リーダーは頻繁に「助けて!」の欄をチェックして迅速に支援を行います。必要であれば他部門の力を借りて積極的に滞留の原因を取り除きます。つまり、徹底して"課題の1個流し"をやるということです。ちなみに、マツダ様の設計部門では、ボードのチーム全員での確認を1日に3回程度行い、徹底して仕事の滞留を排除しておられるそうです。
このようなWIPボードを用いた仕事の進め方は、週に1回進捗会議を行う前時代的なやり方とは全く異なるものです。リーダーはタイムリーにメンバーに支援の手を差し伸べることができますし、支援の手を差し伸べてもらえる前提でメンバーが仕事を進めることができるので、メンバーの心理的安全性も高まるというわけです。また、目の前の課題が明確になり、それを順次迅速に解決することで一人ひとりや組織としての能力が向上する効果も期待できます。
AM社でWIPボードを未導入の職場はこの機会に是非導入いただき、仕事の滞留を排除し、働き方改革に繋いでいただきたいと思います。なお、「助けて!」のところにメンバーが躊躇なく附箋を移動するには、リーダーが喜んで支援の手を差し伸べる姿勢を継続することが重要です。
※このサイトはパナソニックグループで働く皆さんが、ご自身のワークスタイルやライフスタイルに合わせて、イントラネットにアクセスできない状況でもグループの情報に触れることができる環境を構築することを目的としています。
本ページのURLや、掲載されているコンテンツを許可なく外部と共有したり、SNS等に掲載したりすることのないよう、取扱いは十分ご注意ください。

